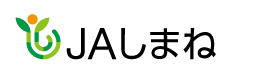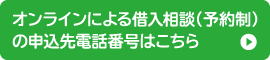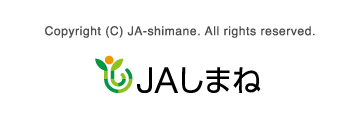つながるコラム「絆」 vol.89 隠岐の島町 ・ 尾見和久さん
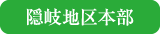

尾見 和久さん(52歳)
隠岐地区本部
少量多品目で島内のニーズに合わせる

島根半島の北方、40~80キロの日本海に浮かぶ隠岐諸島のひとつ、隠岐の島町。農業といえば水稲や畜産が中心で、本格的に野菜を生産する人は少数です。そのため、島内で売られている野菜は島外から仕入れてきたものが多く、船の運航状況によっては流通が左右されることも。尾見和久さんは島内で求められているものを安定供給しようとニーズに合わせ、少量多品目で野菜や果樹、野菜苗などの生産に取り組んでいます。尾見さんは松江市の農業高校を卒業後、隠岐の島町に戻り土木建設会社で働いていましたが、母親が体調を崩したことや地元のために貢献できることはないかと考え5年ほど前に就農しました。現在は父親の博久さんとともに農業に取り組んでいます。
できる限り農薬を抑えて安心でおいしい野菜づくりを目指す

できるだけ農薬を使う回数を減らした生産を意識しているという尾見さん。農薬を基準内で有効的に使いつつ、シュンギクを混植して害虫被害を防ぐなどコンパニオンプランツの力も借りています。この他にも太陽の熱を利用し、地温を温めて土の中の害虫や病原菌、雑草を抑える太陽熱消毒を行っています。土壌消毒をするようになったのにはこんな経験が。タマネギ苗を育てる際に立ち枯れ病や発芽不良に悩んでいた際に、一度試してみたところ5割程度だった発芽率が8~9割に改善したのだそう。それからは太陽熱消毒で土の状態をリセットするように。尾見さんは「特にキュウリなんかは根こぶ病になってしまうと回復することなく収量が落ちてしまう。一度、土をリセットすることで次に何か起きたときに対応に悩まずに済むんです」と話します。
加工品づくりも隠岐の島町産で

尾見さんの畑の近くには「そば工房おみ」の看板を掲げた建物があります。これは父親の博久さんが30年前に農業を行いながら立ち上げた郷土料理「隠岐そば」を提供する店舗兼加工場。「そば工房おみ」では、とにかく島のもので作ることにこだわり、尾見さんが種まきから収穫まで行ったソバと島内で生産されたソバを使い、隠岐の島町産100パーセントの蕎麦を製造。そのほとんどが島内で消費され、昨年末は約7000食分を作り多くの人のお腹を満たしました。 また、昨年には加工場を整備して漬物の営業許可を取得し、漬物製造にも取り組んでいます。付加価値が付くことで単価があがった他にも良いことが。これまでは、形の悪い野菜などは販売に向かないため、やむを得ず廃棄していましたが、漬物用として活用できるようになりました。「見た目が悪くても漬物にすれば気にならなくなります。そのため廃棄する野菜がかなり少なくなりましたね」と尾見さんは話します。
「考えること」が忙しい毎日の息抜きに

年間を通して約70~80種の野菜などを生産する尾見さんは、息をつく暇もないほど次から次へと作業に追われ休みのない日々を過ごしています。収穫や剪定などの作業で腱鞘炎になったことも。そんななか、農機を修理したり野菜のコンテナを積みやすいように配達用の車の荷室を改良したりなど考えて手を動かすことが良い息抜きになっているそう。尾見さんは「結局作業になってしまいますが、一番楽しみと言えば楽しみ。試行錯誤しながら次どうしようかなと考えるのが好きなんです」と笑みをこぼします。
島で作った新鮮な農産物を島の人たちに届けていく

たくさんの野菜などを島内に流通させているなかでも、やはり普段使うことの多いトマトやキュウリ、ナス、タマネギなどの品目の需要が高いそう。島の中で求められているものを安定して供給できるよう取り組む尾見さんの目標は地産地消。「ブランド化して島内から本土などへ出すのもひとつの考えですが、やっぱり原点は地産地消。島で作ったものを島の人たちで消費してもらい、中間コストのかからない新鮮なものをお届けしていくのが一番の目標」と意気込みます。さらに、品種・品目を増やしていくことを視野にいれている尾見さん。今年は収穫物が減る10月後半から12月にかけて収穫シーズンを迎えるキウイを商品として販売していけるよう、樹を這わす棚づくりなどに挑戦しています。尾見さんは「トウモロコシや追熟のいらないサツマイモなど品種・品目を増やしていきたいですが年間の栽培計画のバランスを考えないといけない。これは今後の課題でもありますね」と話します。
現在、隠岐の島町では関係機関が連携し、町内産の野菜を生産する新規就農者の募集に力を入れています。尾見さんの取り組みが、これから野菜生産を目指す人たちの道しるべになっていくことでしょう。取り組みが広がり、町内産の農産物であふれるのもそう遠くない未来かもしれません。